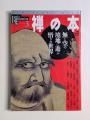2009年 A5判 ソフトカバー P236 カバー僅スレ
岩手県岩泉で1950年代から著者が集めてきた聞き書きから、前半部では山神、天狗、ヒヒ、落人、牛方や相撲取りの武勇伝ほかさまざまな昔話を、後半部は人生儀礼・年中行事などの習俗に関する証言を紹介する。
『河童を見た人びと』『座敷わらしを見た人びと』に続く、「岩手岩泉物語」三部作の完結編にあたる一冊。
目次:
東北文化史の古層へ(石井正己)
(一)柞の章
{山の神に出遇った人/山男の草鞋/山男にさらわれた娘/跡石/人身御供とヒヒ/天狗山から鼓の音/天狗山の雨乞い行事/天狗に殺された十二人の神楽団体/ツチグモと呼ばれた種族/赤ひら様と山姥/モーレン/椀の明神/湯船の明神/星神様とヒヒの歯/ヒヒの松脂/ヒヒの経立と護身用の弾/麻のけんか/長慶天皇御陵/迷い森/落人の伝承 山屋どん/大畑のおじいさん/落人の家宝/荒駒平太蒼前神社/姥捨て山/岩谷の鬼と地名/オイデ山とアイヌの宝/砂金のかめ/アイヌと旭川自衛隊員/北海道のアイヌと皆の川/舟木御山/村に福をもたらした片目の蛇/天然の岩のご神体を拝む/七座大明神/大鳥の山の神様の松}
(二)黄葉の章
{宇部ご官所のご用相撲・安家村の小雀/牛方長作と石尊真石流/相撲一座ご所車と牛方長作のけんか/牛方長作の怪力/侍くとれと牛方長作/普代村太田名部の長太/百姓には百姓の杖がござる/侍は牛方の鞭で殺さぬ程度に/牛方長作と一揆/牛方同士の衝突・茂市の長作/怪童・助六/南部鍋という相撲取り/有芸村コチカミ家の力持ち/有芸村大清水家の力持ち/安家村嘉村家の力持ち/浜人が山人を呼ぶとき/桐買い/姑の麻糸/食えない木の葉/土を食べた話/妖怪アグドコロバシ/鱒の助と鮭の助/オゲエのオオポ/光る山/光る石/大杉さま/宮古港海戦こぼれ話}
(三)楓の章
{一の楔をお抜きぁんせ/猿沢の暮らしの習慣/結婚前夜の垢離取り/臼/ヒエ飯の作法/荷用椀と種物量り椀/神楽宿のシトギの花掛け/隅の粥(すみのけえ)/建前祝いのシトギの花掛け/泥棒祭り/土葬のころ/乙茂神楽/白砂糖を食べない産人の村/真さんと魔避け装束の女/女と男の魔避け/お歯黒と権現様/牛方のおみやげ/中里村の門念仏/懐妊した女性が死んだとき/鹿おどり/お座敷の食いくらご/鉤付け(自在鍵)の歯の付け方/奥州藤原時代の四つ目椀/「クマンプクジ」/岩泉地方の餅搗きうた/産さぬ衣}
(四)桔梗の章
{上中村家の門松迎え/小向家の若水迎え/清水家の若水迎え/各家の若水迎えの祝詞/やらぐろとやらくろ/年々カツさんの若水迎え/年縄の藁買い/浜の門松/俵箸/一月二日の仕事始めの風景/一月五日の樽開き}
(五)野菊の章
{八岐大蛇と小正月行事/小正月のシトギの花掛け/カラスの団子/一月十五日神様詣りの風景/エブラを飾る/丸餅/アワ穂/松橋のまゆ人形/やませを聞く八幡様のおこもり/桑取り子/薪木などの年取り/嫁叩き/穀類の世中見/やーらすり/草責め/鍋の乾きを見る世中見/月の世中見/マスに入った月光/水飲み様の月の出を拝む/ヒエ・アワのお膳/クルミの殻や大豆のたくらべ/ナマコ引き/成り木責め/浜の小正月風景/いとはぎ/釜津田の踊り込み/まゆ買い/皆の川の小正月/一月十六日の背の高い男/一月十六日は精進日}
(六)大花野の章
{お方追ん出し考/二月正月/八皿/やませを聞く女たち/昔の節分/三月三日の桑祝ぎ/三月三日の世中見/三月三日のニラの摘み初め/端午の節句・祝い申す/ヨモギとショウブは夫婦なり/端午の節句・青色団子の世中見/端午の節句の端午膳/端午の節句の青い餅/頼みの朔日/十一月十七日・十八日/十二月九日の大黒様の年取り/女の年取り膳}
詩 人類誕生
あとがき
関係地図
索引