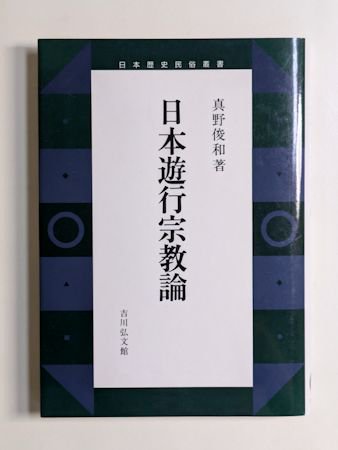平成4年2刷 A5判 カバー僅スレ、端僅イタミ、内側時代シミ
“遊行の聖と定住生活者との交渉を軸に、民衆の信仰を見つめなおし、新たな日本宗教論を構想する注目の書。”(宣伝文)
“古来、人びとは生活のなかでさまざまな機会を通して神仏の霊威にふれ、遊行の聖たちは、社会の外から不思議な力をもって訪れてきた。遊行漂泊の宗教とは、定住する生活様式の彼岸に隔絶した宗教ではなく、いわば定住生活者たちの鏡として、多様な価値観の源泉となった。本書は、遊行聖の宗教を通し、新たな日本宗教論を構想しようとする。”(カバー裏紹介文)
目次:
緒言
序章 日本宗教の遊行性と聖
一 はじめに ―霊場の時代―
二 霊場の発生と成長
三 生と死をこえる空間
四 民衆と霊場
【第一部 巡礼論】
第一章 近代における旅と宗教 ―「まれびと」の変質―
一 旅の喪失
二 近代日本と四国遍路
三 巡礼の規制と保護
四 結語
第二章 講と霊場参詣
一 はじめに ―現代社会と講集団―
二 民俗社会と講集団 ―その多様性―
三 成人儀礼と巡礼講
四 大師講と新四国霊場
五 結語 ―講・在家の宗教集団―
第三章 巡礼行者の宗教的達成
一 はじめに
二 巡礼思想の自覚
三 巡礼の理念と教団の論理
四 飛行する行者
五 曼荼羅の旅
第四章 弘法大師の母 ―あこや御前の伝承と四国霊場縁起―
一 はじめに
二 あこや御前の伝承
三 「高野の巻」
四 弥谷寺の伝承
五 慈尊院の伝承
六 結語 ―高野山から四国霊場まで―
第五章 四国遍路の行者とその宗教活動 ―宥弁真念『四国福礼功徳記』を中心に―
一 四国霊場記三部作の成立
二 宥弁真念
三 『四国編礼功徳記』と真念および寂本
四 結語
【第二部 民俗宗教論】
第一章 室町期における宗教の風流化と寺社参詣
一 はじめに
二 参詣講の成立
三 寺社参詣の話
四 宗教の大衆化 ―風流と遊楽―
第二章 山の法師と里の勧進
一 山の法師の飛鉢法
二 会津恵日寺のイナバツ
三 能登石動山の知識米勧進
四 山の法師の里勧進
五 結語
第三章 冥界からの救済 ―地蔵信仰を題材に―
一 もう一つの『信我物語』
二 『地蔵菩薩霊験記』と地獄冥界譚
三 地獄冥界譚と民俗宗教
四 結語
第四章 たたり・怨霊・異人 ―個と社会の葛藤をめぐって―
一 はじめに ―懲罰とたたり―
二 膨脹する個 ―崇徳院の怒り―
三 たたりのパラドクス ―異人と民俗社会―
四 結語
補論 民間信仰論から民俗宗教論へ ―仏教民俗論の前提として―
一 はじめに
二 民間信仰論の意義
三 「共同体」からの離陸 ―ムラの消滅とともに―
四 ヒジリへの関心
五 結語
あとがき
成稿一覧
索引