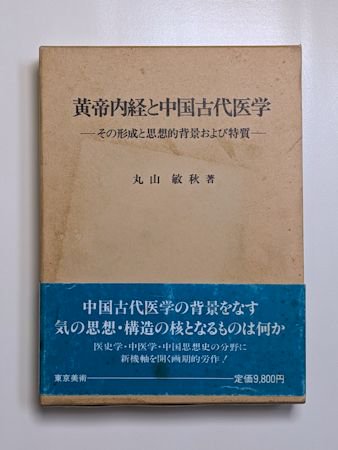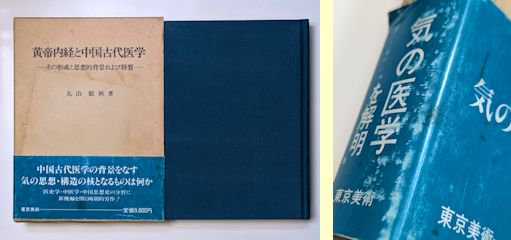

昭和63年2刷 A5判 P426 帯スレ、時代シミ、角少破れ 函ヤケ、時代シミ 本体背ヤケ
“中国古代医学の背景をなす気の思想・構造の核となるものは何か
医史学・中医学・中国思想史の分野に新機軸を開く画期的労作!”(帯文)
目次:
【序説】
一 本書の目的および意図
二 時代設定について
三 各章の梗概
四 資料について
【第一章 天・気・陰陽五行 ―〈内経医学〉の思想史的背景・その一―】
第一節 天の観念と天人相関思想
一 人格的主宰者としての天
二 先秦儒家における天の観念
三 先秦道家における天の観念
四 秦漢期の天人相関思想
第二節 気と万物
一 気と自然界
二 気と万物の生成
第三節 陰陽五行論の特質
第四節 五行の概念と五行論の特質
【第二章 養生思想の展開 ―〈内経医学〉の思想史的背景・その二―】
第一節 道家の養生思想
一 『荘子』の養生説
{(一)生の認識/(二)養生の要諦 ―養生主篇と達生篇―/(三)養神と養生}
二 「淮南子」の養神的養生説
{(一)生の尊重/(二)養神的養生説}
第二節 貴生・全生の思想
一 楊朱とその後学者たち
二 『列子』楊朱篇における貴生・全生説
三 『呂氏春秋』と『荘子』雑篇における貴生・全生説
第三節 神仙的養生説
一 神仙の希求
二 神仙と仙術
三 神仙説の思想的背景
【第三章 呪術から医術へ 】
第一節 医術の母体としての呪術
一 殷代の疾病観
二 巫と医療
三 巫から医へ
第二節 医の制度と民間医の活躍
一 「周礼」の医事制度
二 民間医の活躍 ―扁鵲と淳于意
第三節 気の思想と疾病観の変化
一 平公の病とその原因
二 気と疾病
第四節 淳于意の医術と医療観
一 淳于意の医術
二 淳于意の医療観
小結
附・馬王堆出土医書について
【第四章 〈内経医学〉の大要
第一節 気の生命論
一 血気と営衛
二 経絡気血の体内ルート
三 蔵府とその機能
四 精神
第二節 自然界と人間
一 自然界と人間の形象的対応
二 自然界と人間の動的対応
第三節 疾病の認識
一 疾病の発生
二 疾病の進行と病理論
第四節 診断と治療
一 診断の原則と方法
二 治療の原則と方法
三 医師の在り方について
第五節 予防医学としての養生
一 道家的養生説
二 陰陽家的養生説
【第五章 〈内経医学〉における心身観の特色】
第一節 先秦〜漢初における心身観の概要
第二節 情動と身体 ―〈内経医学〉における心身観(1)
一 志意と五情
二 情動と疾病
三 目と精神
第三節 精神疾患に対する病理認識 ―〈内経医学〉における心身観(2)
一 精神疾患
二 癲と狂
三 その他の精神疾患について
第四節 祝由と夢 ―〈内経医学〉における呪術的医療の認識―
一 祝由と医術
二 夢の認識
【第六章 〈内経医学〉と陰陽五行論】
第一節 〈内経医学〉における五行論の適用
一 五行論の性格と問題点
二 五行の配当
三 相生・相剋論の適用
四 陰陽論と五行論
五 まとめ
第二節 四時の認識と問題
一 古代中国人の季節観
{(一)四時の認識と時説/(二)四時と疾病}
二 〈内経医学〉における四時の認識と問題点
{(一)四時と人体/(二)四時と疾病/(三)四時と五行の問題}
三 〈内経医学> 以降の展開
第三節 三陰三陽の起源と展開
一 二陰と二陽
二 経脈と三陰三陽
三 三陰三陽説の展開
{(一)三陰三陽における陰陽の量/(二)季節の区分から〈運気論〉へ/(三)『素問』熱論篇と『傷寒論』}
四 まとめ
【第七章 『黄帝内経』の伝来と版本 ―書誌的考察・その一 ―】
第一節 『素問』の伝来と版本
一 『素問』の伝来
二 『素問』の主要な版本と注釈書
第二節 「霊枢」の伝来と版本
一 『霊枢』の伝来
二 『霊枢』の主要な版本と注釈書
第三節 『甲乙経』と『太素』 ―『黄帝内経』の別伝のテキスト―
一 皇甫論と『甲乙経』
二 楊上善と『太素』
第四節 『太素』と『素問』『霊枢』の比較考察
【第八章 『黄帝内経』の成立について ―書誌的考察・その二―】
第一節 『素問』の成立についての諸説
一 黄帝時代の作とする説
二 戦国時代の作とする説
三 周〜秦時代の作とする説
四 秦漢時代の作とする説
第二節 『霊枢』の成立についての諸説
第三節 『素問』の巻数の問題
一 問題の所在
二 森立之の「八素説」
{(一)「八索」と「八素」/(二)「八素」と『素問』}
三 原初『素問』の巻数
第四節 黄帝と医学 ―『黄帝内経』の成立事情に関する一考察―
一 『黄帝内経』の論述形式と学派形成説の問題
二 黄帝伝説と医学
三 黄老思想と医学
四 まとめ
結語
あとがき