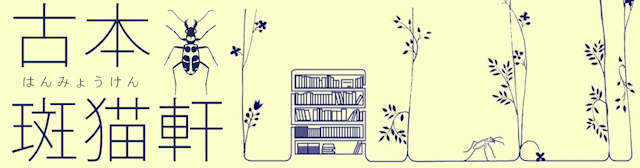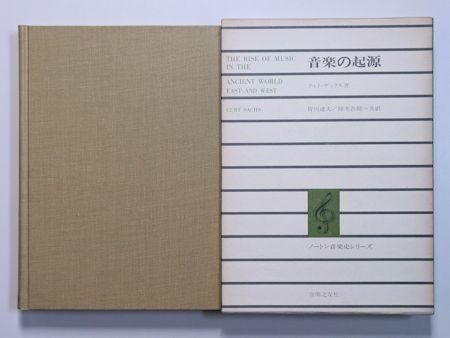音楽の起原 クルト・ザックス 訳:皆川達夫、柿木吾郎 ノートン音楽史シリーズ 音楽之友社
昭和53年4刷 A5判 P413 函ヤケ、少汚れ
商品の説明
昭和53年4刷 A5判 P413 函ヤケ、少汚れ
副題:東西古代世界における音楽の生成
“民族音楽学の世界的権威としてあまりに有名なクルト・ザックスの主著。各国民族の音組織の性格や特質がその生成過程を通し音楽的、歴史的に見事に解明される。”(宣伝文)
目次:
序文
第1章 音楽のいろいろな起源
〔1〕古代社会の音楽 {いろいろな音楽起源論―古代音楽の研究から明らかになったその起原―音楽は歌から始まる―古代音楽の陶酔的性格―シャーマンの歌―古代音楽の社会性―その独特な歌唱技術}
〔2〕比較音楽学とその方法論 {初期の誤謬―円筒録音機―採譜―セント表示法}
〔3〕いろいろな旋律様式 {吟誦詩―一音旋律―二音旋律―ヴェダ様式―反復様式―シンメトリー―3度4度の旋律―最初の進化―女性の貢献―一層大幅の進化―音のひらきと音程―テトラコルドとペンタコルド―ヨーロッパのわらべ唄にみる初期的な旋律の進化}
〔4〕リズムと楽器 {初期のリズム―拍手と打奏―ドラムのリズム―器楽}
〔5〕ポリフォニー {いろいろな平行―ドローンとヘテロフォニー―アンティフォニーとカノン}
〔6〕結論
第2章 西オリエント
〔1〕高度文明と音楽 {伝説・法律および論理―音楽家のカースト―エジプト・スメル・バビロニアの音楽構成―聖書に現れる音楽―イエルサレムの神殿―外国人といろいろな音楽圏}
〔2〕一般的音楽理論 {テトラコルドとペンタコルド―音組織の種別―旋法とその見分け方―音階―《高い》と《低い》}
〔3〕古代西オリエントの音楽 {エジプトに見る史実―上下反復式原理―指孔に見る音組織―等間隔分割―ナカート墳墓のリュート奏者―分割式原理と季節―《倍音》―歌手の皺と手―ユダヤの音楽―神への叫びと沈黙の祈り―旋律型および聖歌朗唱―アクセントとネウマ―ユダヤ語の韻律とリズム―女達の歌―歌詞の部分対応性―アオピンティフォニーと応唱歌唱―シリア・アルメニア・コプト・エチオピアの数会音楽―ポリフォニー―ドローン― ハープの和音}
〔4〕結論 {モロク神の灼熱の手に焼かれる犠牲の叫び}
第3章 東アジア
〔1〕全般的特色 {中国と日本―卑俗な音楽―上品な音楽―音楽の精神性―単一音の音楽―宇宙の音楽―宇宙論的内包―天体のハーモニー―音楽と尺度―音楽の修正}
〔2〕十二律 {伶倫の使命―標準音―十二律―神秘哲学―種々の困難―陽と陰―上昇と下降― 日本に見る平行現象}
〔3〕音階 {中国の音階―旋法―日本の音階―長3度型5音音階―マラヤの音階―ペログムンガング―サレンドロ―シャム・カンボジア・ビルマの音階―《変》―7音音階および長音階}
〔4〕メロディとリズム {能楽―歌唱樣式―鬼神―中国楽劇―言語旋律―リズムと形式}
〔5〕記譜法 {バリの譜本―表音記譜法―ネウマ―《グィドの手》―タブラチュア}
〔6〕ポリフォニー {ヘテロフォニー―和音―右方楽と左方楽―雅楽のポリフォニー}
〔7〕オーケストラ {大宇宙と小宇宙との掛橋―巨大な宮廷オーケストラ―外来楽オーケストラ― ガムラン―カンボジアとシャム―影絵芝居}
第4章 インド
〔1〕ヴェダの詠唱
〔2〕絵画史料ならびに文献史料 {レリーフ―バラータ物語}
〔3〕音階 {各音―記譜法―スルティ―グラーマ―ムルチャーナ}
〔4〕ラーガ {旋律型―原型と変奏―伝説―水と火の魔法―ジャーティ―分類―演奏の時刻―ガマカ―音の震わせ―歌の技巧―ドローン}
〔5〕リズムと形式 {詩の韻律―ターラ―ドラムの技巧―アーラーパとラーガ}
〔6〕結論 {貸方と借方}
第5章 ギリシャとローマ
新しい研究方法
〔1〕諸史料 {残存する曲目―残存する論文―虚説}
〔2〕記譜法{ピッチ―器楽用記譜法―声楽用記譜法}
〔3〕ジェネラ(音組織の種類) {ディアトニック―クロマティック―エンハルモニック―エンハルモニオンの最盛期―その原型―日本に見られる平行現象―3弦のライア}
〔4〕クロアイ(変化音組織の種類)
{アリストクセノスの示すもの―プトレマイオスの示すもの―ギリシャの音楽は「東洋的に」響いた}
〔5〕 初期の旋法 {ハルモニア―ドリア属―フリギアとリディア―再び日本に見られる平行現象―その系統}
〔6〕完全音組織 {音組織―各調の排列―正格性の衰微―エオリア―初期のミクソリディア―秘密の音階―ライアの調弦―F音列―接合式音組織―階名唱法―初期の誤り}
〔7〕現存する作品 {分析法―残存作品についての分析研究}
〔8〕エトス {問題―旋法―ピッチ―ラーガ・マカーム―力動的神秘的緊張―ハルモニア―ラーガ}
〔9〕健康と教育 {同種療法―異種療法―教育学}
〔10〕対位法 {伴奏―協和音―不協和音}
〔11〕アクセントとリズム {抑揚リズム―強弱リズム―詩的リズムと衝動的リズム―残存するリズム―リズム型―テンポ}
〔12〕形式 {進化と沈滞―合唱形式―ディテュランポス―ドラマ―独奏音楽―ノモス― コンクール}
〔13〕ローマ
第6章 イスラム音楽に残るギリシャの遺産
「アラブ」の様式
〔1〕音階と旋法 {7音音階―17音音階―転回とコンビネーション―3/4音}
〔2〕マカーム {いろいろな型―エトス―治療学―宇宙論的内包}
〔3〕リズム {韻律―詩からの解放―リズム型―ドラム奏法―ポリリズム}
〔4〕ポリフォニー {ヘテロフォニー―ドローン―オスティナート―協和音}
〔5〕形式 {タクシム―ペシュレヴ―ヌーパ}
第7章 ヨーロッパならびに長調、短調への道筋
{勇敢な戦士のハーモニーと獣的な歌―北方音楽と南方音楽の間の谷間―中世の調性に関する謎―3度の連鎖―ランディーニの6度―グレゴリオ聖歌もまた非東洋的―われわれの五線譜の意味―交錯―長調は「ドイツ的」といわれる―長調への進化―導音とムジカ・フィクタ―ウグリック・フィンの平行現象―中国・インド・ギリシャ・イスラム音楽における長調への傾向―声楽様式と器楽様式の衝突―歌わないオランダ人と嘶く雄馬―器楽様式におけるハーモニー―リズム―韻律とモーダル・リズム}
エピローグ
訳者あとがき
索引