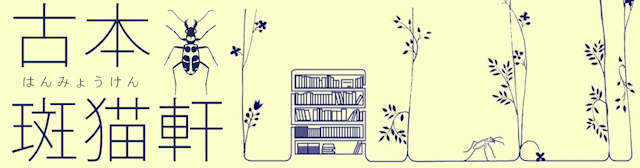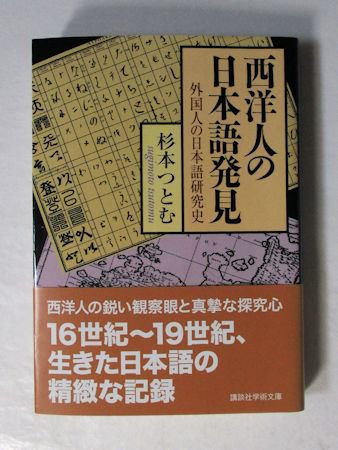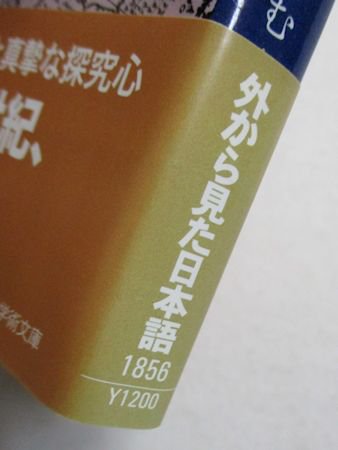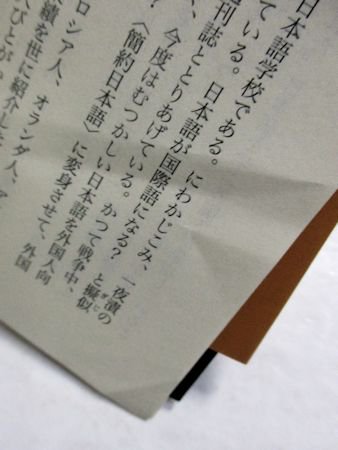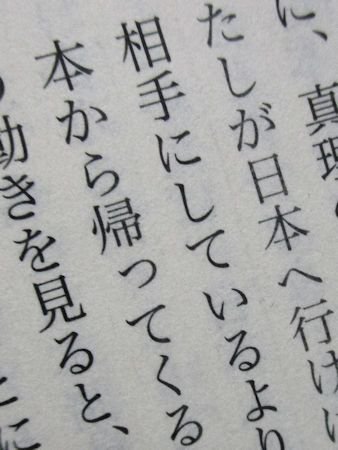西洋人の日本語発見 外国人の日本語研究史 杉本つとむ 講談社学術文庫
2008年 文庫判 P394 帯背ヤケ カバー袖および内側複数箇所にセロテープ跡 小口少汚れ P3〜22およびP65〜67にかけて薄く鉛筆引線消し跡 少折れ跡
商品の説明
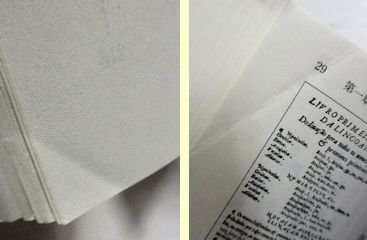
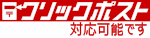
2008年 文庫判 P394 帯背ヤケ カバー袖および内側複数箇所にセロテープ跡 小口少汚れ P3〜22およびP65〜67にかけて薄く鉛筆引線消し跡 少折れ跡
“西洋人の鋭い観察眼と真摯な探究心
16世紀〜19世紀、生きた日本語の精緻な記録”(帯文)
“一五四九年に来日したサヴィエル以降、ポルトガル・ロシア・オランダなどの人びとが、布教や交易、漂流民との交流等を通じて日本語に触れた。彼らは、口語と文語の使い分けや敬語など複雑な構成の日本語を、鋭い観察眼で分析し、精綴な辞書を作りあげた。それは、方言や俗語など当時の生きた日本語の貴重な記録でもある。彼らの真摯な研究成果と、日本語観・日本人観を紹介する。”(カバー裏紹介文)
目次:
まえがき
凡例
第一章 吉利支丹の世紀と日本語の世界
1 サヴィエルと日本語
2 A・ヴァリニァーノと日本語
3 I・ロドリゲスの日本語学
4 日本語の構造と助辞
5 日本語、その品詞分類
6 日本諸国の方言、観察と記録
7 日本語の真髄・敬語の探究
8 書状の書き方と作法
9 日本語文典と辞書の編集
第二章 魯西亜人とその日本語学
1 魯西亜と漂流民と日本語学事始
2 ゴロヴニンと日本・日本語観
3 幕末、ヘダ号建造とI・ゴシケヴッチ、橘耕斎
4 I・コシケヴッチと日本語観察
5 『和魯通言比考』と『早引節用集』『日本植物/動物誌』
6 日本語学のその後
第三章 オランダ人とその日本語学
1 オランダの東洋語研究
2 出島の商館長《カピタン》と日本研究
3 商館長とその日本語観
4 シーボルトとホフマンの出逢い
5 D・クルチゥス『日本文法試論』
第四章 J・J・ホフマンとその日本語学
1 ホフマンと『日本文典』
2 日本語文法と語源研究
3 ホフマン、日本語学の座標
4 ホフマン以後の日本語学
第五章 十九世紀ヨーロッパの東洋学者と日本語学
1 ヨーロッパの東洋学者たち
2 L・パジェスとL・ロニーの日本語学
3 イギリス人宣教師と日本語学
第六章 幕末、宣教師と日本語研究
1 幕末の日本とアメリカ人宣教師たち
2 S・R/ブラウンと生きた日本語観察
3 聖書の翻訳と語学教育
4 J・C・ヘボンと和英辞典の編集
5 ヘボンと日本語と聖書
国際舞台へおどりでた日本語―まとめにかえて
主要参考文献
あとがき
学術文庫版あとがき